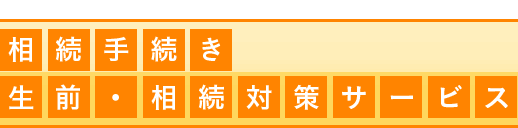
![]()
![]()
「相続人」「相続放棄」など、最低限知っておくべき用語や知識について、ご説明いたします。
相続をスムーズに終わらせるためにも、このサイトをご活用下さい。
人が亡くなれば必ず発生するものが相続です。相続とは、亡くなった方の財産・負債や権利・義務などの法律的な関係が他の人に移ることです。
相続によって遺産を受け継ぐ人を「相続人」と呼び、亡くなった方との間に一定の身分関係がある人が「相続人」となります。亡くなった方のことを「被相続人」と呼びます。
相続人になる人が「相続します」と宣言しようとしまいと、人が亡くなった時には自動的に相続が発生します。ですから、もし相続する財産がマイナスの場合や、「相続をしたくない」場合には、相続しない事を宣言しなければなりません。この宣言のことを「相続放棄」と言います。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てなければ、強制的に相続させられてしまいます。相続とは相続人本人の意思とは関係なく発生するということを知っておきましょう。
原則として相続は人の死によって開始しますが、生死不明の場合はどうでしょうか。家出をしたきり何年も行方不明で生きているのかも判らない、または乗っていた船が沈没した死体が発見されなかったなどの場合です。このような場合には、一定の要件を満たす行方不明者を死亡したものとみなす失踪宣告制度を利用することができます。
家庭裁判所によって失踪宣告がなされると、その行方不明者は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始することになります。
行方不明者につきその生死が7年間不明であるとき、または戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇してからその生死が1年間不明であるとき。行方不明者の相続人などから家庭裁判所へ申立することになります。
・まずは誰が相続人なのか?
・財産がどれだけあるのか?
・遺言は残されているか?
・財産をどのように分けるか?
・相続税は発生するのか?
・不動産等の名義変更に必要な準備は
ここまでを済ませて初めて、銀行や法務局に手続にいけるのです。相続が完了するまでの手続は非常に多く、かつ面倒でとても複雑な手続を踏まなくてはなりません。途中に間違いがあればすべてやり直しになってしまうことだってあります。相続をスムーズに終わらせる為にも、このサイトを活用して必要な手続きを知ってください。
財産のある方が遺言なく亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、定められた相続分が相続されます。これを「法定相続」といいます。
民法上は、定められた相続人へ定められた相続分を渡すことになっているのですが、遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が自由に決めることができるのです。
ただしこの場合には、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。では、相続の順序や割合はどのように決められているのでしょうか?
遺言書なく被相続人が亡くなった場合、法定相続は以下のようになります。
| 順位 | 法定相続人 | 割合 | |
| 1 | 子と配偶者 | 子=1/2 | 配偶者=1/2 |
| 2 | 直径尊属と配偶者 | 直系尊属=1/3 | 配偶者=2/3 |
| 3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=1/4 | 配偶者=3/4 |
◆配偶者は常に相続人
◆直系尊属は、子がいない場合の相続人
◆兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書が、いくら亡くなった方の自由意志を反映させるものと言っても、後々もめないようにするには、作成する時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。
思わぬ方が相続人になることも…
相続は亡くなった方から相続人へ財産などを移転することですから、そもそも相続人が誰なのかが分からなければ手続はできません。
「調べなくても大丈夫だろう。」と考えていると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。しっかりと誰が相続人であるかを把握することが重要です。
想像もしなかったような人が相続人になることも少なくはありません。正しい相続人の知識があったら、絶対に調査の手抜きはできません。誰が相続人になり得る権利をもつのかは民法で決められています。
原則として遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。
・配偶者 どんな場合でも相続人になります。
・子(養子、胎児含む) 第一順位の相続人になります。子がすでに亡くなっていて、その代襲者(孫など)がいる場合は、代襲者が第一順位の相続人になります。孫もすでに亡くなっているときは、さらにその子が相続人となります。
・直系尊属 直系尊属(父母、祖父母など)のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。
・兄弟姉妹 第三順位の相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。
配偶者と子以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ相続人になります。つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。
・配偶者と子・養子・胎児(代襲相続人を含む)
・配偶者と両親(または一番親等の近い直系尊属)
・配偶者と兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)
・配偶者のみ
・子・養子・胎児(代襲相続人を含む)のみ
・両親(または一番親等の近い直系尊属)のみ
・兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ
相続人がはっきりしていないと、なんら権利をもたない部外者がまるで相続人であるかのように振舞い、話を混乱させるケースもありますので、調査の段階で「相続人」と「部外者」をはっきりさせることが重要です。
①誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。
②通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
③子供(代襲者を含む)がいない場合は両親をはじめとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取り寄せて調査します。
④直系尊属が全員亡くなっている場合は兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。意外に思われるかもしれませんが、相続人の数が当初考えていたより遥かに増えるケースはかなりの割合であります。被相続人がなくなって突如姿を現す相続人もいるのです。
相続人確認の調査の手を抜くと、後で見落としていた相続人から相続の回復を請求され、すべてやり直しになる可能性がありますので慎重に調査しましょう。
法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子といいます。そして法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子であっても、父親に認知されたときは非嫡出子として父親の第一順位の相続人となります。その後、父母が婚姻した場合には嫡出子となります(準正)。
ただし非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分になってしまいます。
養親と養子との合意により成立し市役所等に届出ることで養親の嫡出子となります。ただし未成年者を養子とする場合には原則として家庭裁判所の許可を要します。
そして養子となることで実親の子であると同時に養親の子でもあることになり、実親または養親のどちらが死亡した場合でも、その相続人となります。
普通養子の場合と異なり家庭裁判所への申立てによってします。原則として6歳未満の未成年者の福祉のために特に必要と認められる場合にのみ養子となることができます。
特別養子縁組が成立すると養子と実親側との親族関係が消滅します。つまり実親が死亡しても相続人となりません。
相続開始時に被相続人の配偶者(妻)に胎児がいる場合には、その胎児は生まれた者とみなされ相続人となります。
また、相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか「財産の半分を譲る」と指定されていた人(包括受遺者と言います)は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協議に参加することになります。
相続放棄した者、相続欠格事由に該当する者、相続廃除された者は相続人となりません。
相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。相続人は自分の相続したい財産の一部分だけを相続することはできません。亡くなった人が持っていた財産や権利・義務のすべてを相続することになりますから、借金も一緒に相続しなければいけないのです。
ですから相続が開始してからできるだけ早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。原則は「すべて相続するか」「すべて放棄するか」のどちらかになります。
相続財産………遺産分割の対象になる財産
みなし相続財産………相続税の課税対象になる財産
祭祀財産………相続財産、みなし相続財産のどちらにもならない財産
確認できた財産がどれに当たるかによって、扱いが異なりますので注意しましょう。
財産がプラスかマイナスか調査し、必要か不要か、その判断ができたら相続するかどうかを決めます。その際できるのは次の3つの選択です。
相続財産を単純承認する
●すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
●特に手続きは必要ありません。
相続財産を放棄する
●負債も含め何も受け継がない選択です。
●相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。
相続財産を限定承認する
●財産が差し引きでプラスなら相続する選択です。
●相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
●一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てできません。
●限定承認によって相続した財産については、相続時に、相続時の価額に相当する金額により譲渡があったものとみなして、譲渡所得税を納めなければなりません。
●なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。
ここまでできたら、いよいよ相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。
相続が発生すると、様々な手続きが必要となります。 そしてその手続きには様々な書類を用意する必要があります。 以下にそのうちの主なものを挙げます。
・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍
相続が発生したこと、相続権が誰にあるのかを証するため
・被相続人の住民票の除票
所有者と被相続人が同一人物だということを証するため
・相続人の現在戸籍
相続人が今現在生存し、相続権があることを証するため
・遺産分割協議書
相続財産を誰が取得するのか、すべての相続人が合意したことを証するため
・相続人の印鑑証明
遺産分割協議書への署名捺印が、本人によってなされていることを証するため
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有者が誰なのかや、担保権などがついているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きが必要になります。
不動産の登記名義を変更しないことも可能ですが、登記名義人から何代もそのままにしておくと、いざ不動産を売却したいと思ったときに承諾を得なければならない相続人の人数が膨大になるなど後々トラブルになる可能性が高くなりますので、不動産の名義変更の手続きはできるだけ速やかに行うことをおすすめします。
大まかに以下の手順で行います。
遺産分割協議の終了
↓
登記に必要な書類の収集
↓
登記申請書の作成
↓
法務局への登記の申請
では、手続きの進め方はどのように行っていけばよいのでしょうか?一般的な流れをおさえておきましょう。
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。登記を申請する法務局に直接問い合わせてみるといいでしょう。それでもよく分からないようであれば、司法書士にお気軽に質問してください。
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
また、登記のプロフェッショナルである司法書士に登記の依頼をした場合には、必要書類の収集、登記申請書の作成、法務局への登記の申請まですべての手続きを司法書士が代理することができますのでスムーズに名義変更できます。
生命保険金については、その受取人がどの様に指定されているのかで分けて考える必要があります。
以下の様に分けてみます。
ケース(1)
特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
ケース(2)
保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
→保険金は自分の固有財産として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(3)
保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
→このケースでは、保険金は相続財産となります。
以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は、「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。
また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として全額が受取人の固有財産となります。
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などです。※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
このケースは、被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。従って、生命保険金は相続財産には含まれず、相続人の固有財産となるとされています。(最高裁判所の裁判例)
受取人が相続人となっている生命保険金は、遺産分割協議の対象となりません。また、受取人が単に「相続人」となっているときは、原則として、相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれ、各相続人は相続分の割合により保険金を取得する、とされています。(最高裁判所の裁判例)
よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
遺産分割をどのように済ませたかによって、手続きは異なりますので、事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出します。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出します。
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出します。
・遺言書
・被相続人の戸籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
ですから「遺族基礎年金」だけが支給されるのかあるいは「遺族厚生年金」がプラスされるかを考えて、間違ってももらい忘れのないようにしたいものです。
年金加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、
国民年金では
1)遺族基礎年金
2)寡婦年金
3)死亡一時金
の3つがあります。
また厚生年金、共済年金では、
1)遺族厚生年金、遺族共済年金
2)遺族基礎年金
の2つがあります。
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で加入期間の3分の2以上、保険料を納めていた人が亡くなった場合、遺族に対して上記の給付がされます。
遺族に対する年金の給付の要件は、年金加入者あるいは受給者が以下のような状況で死亡したときです。
1)勤労している加入者が死亡したとき
2)仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
3)老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
4)1級か2級の障害給付を受けていたとき
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡したとき、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基礎年金が支給されます。
また、子が20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級である場合も支給されます。
これらの遺族でも受給するには次の条件が定められています。
1)年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
2)内縁関係も含みます
3)認知された子も含みます
4)妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止されます
厚生年金、共済年金に加入していた故人の遺族には、遺族基礎年金に
遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡したとき、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基礎年金が支給されます。
また、子が20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級である場合も支給されます。
これらの遺族でも受給するには次の条件が定められています。
1)年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
2)内縁関係も含みます
3)認知された子も含みます
4)妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止されます
厚生年金、共済年金に加入していた故人の遺族には、遺族基礎年金に遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。
請求人
・年金加入者、年金受給者の遺族
請求先
・住所地の社会保険事務所(年金受給者死亡のとき)
・勤務先の社会保険事務所(厚生年金・共済年金加入者の死亡のとき)
・市区町村の役所(国民年金加入者の死亡のとき)
請求書類
・国民年金
・厚生年金保険
・船員保険遺族給付裁定請求書
・年金手帳
・戸籍抄本
・死亡証明書
・銀行通帳
・印鑑
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「引き継ぎません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、「借金」などの財産も存在します。借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
一般的に借金だけを相続した場合、損はしても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。ただし、条件がいくつかあります。前述の通り、相続人は自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄ということも可能です。ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
相続放棄以外のもう一つの手段として、限定承認という方法があります。限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。借金の方が多いけど、どうしても財産を相続したいという場合や、借金の額が不明であるという場合などに有効です。
限定承認をするにも、いくつか条件があります。相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければならないこと。また、相続人が複数いる場合は、相続人全員が一致で限定承認する必要があります。
もしも何もせずに相続開始を知った時から3ヶ月を経過してまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。
相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。相続財産を単純承認する方法と限定承認する方法です。
単純承認とは、相続財産を負債も含め無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。自分に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間と言います)に限定承認か相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が自分に相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、又はわざとこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、たとえ相続する意思がなかったとしても、単純承認したことにになってしまいますので注意しましょう。
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。つまり、相続の承認はするけれども、被相続人の債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継するプラスの相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1)相続人全員の総意が必要となります。
2)相続の開始を知った時から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額についての譲渡所得税が課税がされます。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
・債務超過しているかどうかはっきりしない場合
・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産の確認を調査して、相続してよいものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。
相続放棄や限定承認の判断は、相続開始を知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。この短期間で、被相続人の財産や借金をしっかり調査しなければなりません。
実際に3ヶ月以内に、全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。このようなときは、限定承認や相続放棄の期間を延長することができます。相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求する事により、この延長は可能となります。ですから、相続財産がプラスかマイナスかが直ぐにはっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合、この延長の請求をおすすめします。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数箇所の不動産を所有していた場合などは、すべての財産を3ヶ月で把握するのは困難でしょうから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。
1)相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合
当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合には、当初の相続人の相続人は、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。
2)相続人が未成年者または成年被後見人である場合
制限能力者(未成年者、成年被後見人)の法定代理人(親、成年後見人等)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。
3)その他、熟慮期間が延長される例外的ケース
被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できることがあります。
相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。問題を回避するためにも、このページで事前に知識を得てください。
被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っているでしょうし、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるでしょうから、不動産登記簿からその存在を確認することなども容易です。
しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。
連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。
債務が全くないと誤信していたために、「自分に相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」以内に相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。
ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。
たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておく必要があります。
放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいのですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続等に拠らざるを得なくなってしまいます。また、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの放棄では、既に相続した財産を処分・費消してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。
相続税に最も大きな影響を与える財産のひとつが不動産です。不動産の財産価値が高ければ高いほど相続税の負担も大きくなるようになっています。 ですから、相続税は不動産の価値、正確には不動産の評価方法によって大きく変わってしまうことがあります。
では、不動産の価値は誰がどのように算出するのでしょう。一般的には、不動産の評価は税理士が路線価と不動産面積から算出します。簡単に言うと、道路には値段が決まっていて、その不動産が接している道路の値段を調べて不動産の面積を数式に当てはめれば、不動産の大まかな価値を算出するのです。
路線価は税務署で調べることができます。ただし、不動産は個別性の非常に高い財産ですから、これだけでは適正な不動産価格は出せません。
しっかりと現地に行って、高低差や、不動産の形、交通手段や周辺の施設をチェックして、それら要素を加味して、最終的に「不動産の価値」を算定するのです。
実は、意外と知られていないのですが、すべての税理士が、この不動産評価を出来るとは限らないのです。なかには、相続税申告に慣れていない税理士もいて、その土地評価が適正ではないことがあるのです。
そのことによって、相続人が払わなくてもいい相続税を払わされて、後になって訴訟になる、などのケースがあります。不動産の評価に不安がある場合は、不動産鑑定士に相談するのも一つの手です。不動産鑑定士とは、不動産の実勢価格を算出する国家資格をもつ人たちのことです。要するに、不動産のプロフェッショナルです。
不動産鑑定士に土地評価を依頼すれば、その不動産を様々な角度から正確に評価をしてくれます。路線価と面積だけの大雑把な数式ではなく、その不動産を個別的に評価してくれます。
税理士が評価して1億円だったものが、不動産鑑定士に評価してもらったら4,000万だった、ということもあり得ます。もちろんすべてではありませんが、相続税が高いと思ったら、不動産の評価が適正になされていない可能性もありますので、相談してみてください。
土地を貸していたり、土地に建物を建てて貸していたりする場合には、不動産の評価額を減少させることができます。上手に利用して、相続税額を減らしましょう。
土地を他人に貸している場合
貸宅地=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地価額とは更地価格のことであり、借地権割合は路線価表に掲載されています)
土地を借りている場合
借地権=自用地価額×借地権割合(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しません)
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合)
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。
| 被相続人要件のみ 満たしている宅地等 |
200平方メートルまで 50%減額 |
| 被相続人要件及び 相続人要件を共に 満たしている 居住用宅地等 |
240平方メートルまで 80%減額 |
| 被相続人要件及び 相続人要件を共に 満たしている 事業用宅地等 |
400平方メートルまで 80%減額 |
| 不動産貸付用の宅地等 | 200平方メートルまで 50%減額 |
建物を他人に貸している場合
貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合)
相続財産である不動産の境界が原因でしばしばトラブルになる事があります。ここでは境界についてご説明します。しっかりと理解し、万が一問題になった際にも対処できるようにしましょう。
境界とは、土地と土地の境のことです。相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界が解らないなどの場合がありますから注意が必要です。
では、境界がはっきりしない場合はどうすれば良いのでしょうか?そんなときは以下のような方法で解決できます。
・土地家屋調査士に相談する
・境界問題相談センターなどの裁判外の紛争解決機関(ADR)に相談する
・筆界特定制度を利用する
・境界確定の訴えを起こす
いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は土地家屋調査士や各県の境界問題相談センターに相談して公正な立場で判断してもらいましょう。
土地の売却は「相続後」が断然お勧めです。その理由は様々あります。
ここでは相続不動産の売却のポイントについて説明します。
・「相続の後」は譲渡税を安く土地を売却
・「相続の後」の土地売却
まとまった土地が売り出される大きな原因に相続があります。先祖代々受け継いできた土地を突然手放すと、隣近所では「あの地主の跡取り息子は何をしでかしたのか」と好奇の目と非難の目で見られてしまいます。しかし、それが相続後の売却だと同情の目で見られます。「あの家は大変だね、相続で土地まで手放すことになってしまって」ということになりますから。
逆に言えば、地主さんがご近所や遠縁の親戚から「とやかく」言われずに先祖代々の土地を売却できるのは相続の後だけです。
「相続なのだから」ということで、非難はされません。もちろん、相続税の支払いや、他の相続人にとの調整のためのやむを得ない売却もあります。しかし、今のような不安な時代に所有財産が土地だけというのは、それこそ不安です。
不動産から金融資産への組替えも必要でしょう。また、次の相続対策のために生命保険に入ろうとしても現金がなくては始まりません。自宅建替えにも現金は必要です。
・看病疲れのお嫁さんのために海外旅行をしたい。
・子供の教育資金を現金で用意しておきたい。
・これを機に借金を清算したい。
そんな普通は「先祖に対して不謹慎な(?)」と言われる用途でも現金が必要なのは事実です。先祖代々の土地売却は、不謹慎ながら「相続の後」がお勧めです。世間体もいいし、そして何より税金も安くなります。
「相続税納税のための財産売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。土地や建物を相続によって取得した人に相続税が課税されている場合に、一定の期日までに相続財産を売却することで、相続税額のうちの一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。つまり譲渡所得額を減らし、それに係る税額を減らす事ができるのです。
譲渡所得額は次のように計算します。
(土地や建物を売った金額)-(取得費+譲渡費用)
ところが期限日の翌日の売却となってしまうと通常の税額となります。特例の趣旨は「相続税納税のため」ですが、法律は「相続税申告期限から3年以内に相続土地を売却すれば」となっていますので、相続税は現金で無事納税が完了していても、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年間はこの特例が適用でき、非課税枠ができるのです。
非課税枠がいくらになるかは少し複雑です。しかし財産のほとんどが土地の場合には相続税額のほとんどすべてが譲渡税の非課税枠になるでしょう。なおこれは必ず税理士に聞いて頂きたい事柄です。当事務所にご相談頂ければ、相続に強い税理士を紹介させて頂きます。
ここでは、相続税について詳しくご説明します。
相続税を正しく理解し、有効活用できるようになりましょう。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に課税されます。相続とは、民法で定められている相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
相続税の申告および納税の期限は、被相続人(亡くなった方)の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失踪宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始します。
※失踪宣言とは、一定期間(通常7年)所在及び生死が不明な人について、家族の請求によって家庭裁判所が失踪宣告することで死亡したものとみなすという制度です。
相続税がいくらになるのかは相続財産がどれだけあるのかによります。よって最も重要なことは、相続税がかかる財産がどれだけあるのかを把握することです。
相続税の対象となる財産は大きく、
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
被相続人の死亡時にその者の所有していた財産のことです。つまり相続人による遺産分割の対象となる財産です。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始前3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は相続財産として上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
相続財産は以下のように分けられます。
プラスに作用するもの
・土地・建物
・借地権・貸宅地
・現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)
・生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
・貸付金・売掛金
・特許権・著作権
・貴金属・宝石・自転車・家具
・ゴルフ会員権
・書画・骨董
・自社株など
マイナスに作用するもの
・借入金・買掛金
・未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
・預かり敷金・保証金
・未払の医療費
非課税財
・お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
・生命保険金・退職手当金のうち一定額
不動産等の相続税の申告は、どのようにして決められているのでしょうか?ここでは相続した不動産の評価方法などを詳しくご説明いたします。
不動産等の相続税の申告は、時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額を元に行います。 相続税の申告でこの相続税評価額の計算が最も厄介であり、かなりの専門知識が要求されるところです。自分でやってできなくはないと思いますが、膨大な時間がかかりますし、その評価額が正しいとも限りません。 ですから、ここは専門家の力を借りるのが無難です。財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものを ご紹介いたします。
土地の評価方法
(1)路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価×(注)補正率・加算率×地積
(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(2)倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額×倍率
(3)借地の評価
路線価方式、または倍率方式の評価額×借地権割合
(4)貸地の評価
路線価方式、または倍率方式の評価額×(1-借地権割合)
(5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
路線価方式、または倍率方式の評価額×(1-借地権割合×30%)
建物の評価方法
(1)自用家屋
固定資産税評価額×1.0
(2)貸家
自用家屋の価額×(1-30%)
次のうち、最も低い金額で評価します。
1)相続開始の日の最終価格
2)相続開始の月の最終価格の月平均額
3)その前月の最終価格の月平均額
4)その前々月の最終価格の月平均額
生命保険金の評価
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
退職手当金の評価
受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
※弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合 死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合 死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額
生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
解約返戻金相当額
その他の評価
1)預貯金……元金+解約利子の手取額
2)利付公社債……発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利子の手取額
3)割引公社債……課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)
4)貸付信託……元金+既経過収益の手取額-買取割引料
5)証券投資信託……上場されているものは3の上場株式の評価に準じ、それ以外は解約請求金額
6)ゴルフ会員権……取引相場×0.7
7)書画・骨董品……専門家による鑑定価額
相続税はどの位かかるの?というご質問をよく頂きます。ここではそんな疑問を解消する為、相続税の決定方法をご説明します。
相続税は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人関係で決まります。下記の相続税早見表でざっくりとした相続税額をご確認下さい。
配偶者は法定相続分については無税になります。また、配偶者が法定相続分を超えて相続した場合でも1億6000万円までは無税になります。なお下表は各相続人が法定相続分どおり相続したものと仮定しています。
下記の2つの場合で相続税は大きく異なります。
| 遺産 総額 |
配偶者 子供1人 |
配偶者 子供2人 |
配偶者 子供3人 |
配偶者 子供4人 |
| 1億円 | 175 | 100 | 50 | 0 |
| 2億円 | 1,250 | 950 | 812 | 675 |
| 3億円 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 1,800 |
| 4億円 | 4,900 | 4,050 | 3,525 | 3,250 |
| 5億円 | 6,900 | 5,850 | 5,275 | 4,750 |
| 6億円 | 8,900 | 7,850 | 7,025 | 6,500 |
| 7億円 | 11,050 | 9,900 | 8,825 | 8,250 |
| 8億円 | 13,550 | 12,150 | 11,075 | 10,250 |
| 9億円 | 16,050 | 14,400 | 13,325 | 12,250 |
| 10億円 | 18,550 | 16,650 | 15,575 | 14,500 |
| 遺産 総額 |
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 |
| 1億円 | 600 | 350 | 200 | 100 |
| 2億円 | 3,900 | 2,500 | 18,00 | 1,450 |
| 3億円 | 7,900 | 5,800 | 4,500 | 3,500 |
| 4億円 | 12,300 | 9,800 | 7,700 | 6,500 |
| 5億円 | 17,300 | 13,800 | 11,700 | 9,600 |
| 6億円 | 22,300 | 17,800 | 15,700 | 13,600 |
| 7億円 | 27,300 | 22,100 | 19,700 | 17,600 |
| 8億円 | 32,300 | 27,100 | 23,700 | 21,600 |
| 9億円 | 37,300 | 32,100 | 27,700 | 25,600 |
| 10億円 | 42,300 | 37,100 | 31,900 | 29,600 |
遺産分割には『指定分割』『協議分割』の2つがあり、遺産分割の方法としては『現物分割』『換価分割』『代償分割』および『共有分割』の4つがあります。ここでは、それぞれの方法を詳しくご説明します。
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことができます。
その方法はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
▶指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらを最優先にすべきです。
▶協議分割
共同相続人全員の協議により行う分割方法。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
▶現物分割
遺産そのものを現物で各相続人に分ける方法です。ただ、各相続人の相続分通りに分けることが困難になることがあります。例えば1筆の土地を相続人の相続分に応じて分筆したり、相続人Aが不動産を相続人Bが現金を相続するという形が考えられます。
▶換価分割
遺産を売却し、その売却益を各相続人で分ける方法です。
▶代償分割
相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して金銭を支払うという方法です。遺産が自宅のみ又は農地であるなど、現実に分割することが困難である場合に有効な分割方法です。
▶共有分割
遺産を相続人が共有で所有するとすることもできます。ただし共有名義の不動産は利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので、注意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しておくことが必要です。後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、その名義を相続人に変更する所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金があった場合にそれを引き出す際にも必要となります。
※失踪宣言とは、一定期間(通常7年)所在及び生死が不明な人について、家族の請求によって家庭裁判所が失踪宣告することで死亡したものとみなすという制度です。
遺産分割をする際に、必要になるものが遺産分割協議書です。ここでは遺産分割協議書を書く際に必要なポイントについて見ていくこといにします。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、話し合いがまとまったとしても、一部の相続人の気が変わり協議の内容について無効を主張することも考えられます。そのような事態は避けなければなりません。
相続財産の名義変更の際にも必要な証明書になりますので、遺産分割協議書の作成をお勧めします。遺産分割協議書の書式や形式などに決まりはありませんから、内容が明確であれば、縦書や横書、自筆やパソコンで作成してもかまいません。
但し、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。
従って、遺産分割協議書には全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。
1)相続人の範囲 相続人が誰であるか明記します。
2)相続財産の範囲
相続財産の中にどのようなものがあるか明記します。
3)分割方法
誰が何を相続するのか、単独所有、共同所有など明記します。
4)新たに相続財産を発見したときの対処方法
協議書作成当時に発見されなかった相続財産が出てきたときの取扱いを決めておくことができます。
(例 相続人全員で改めて協議し分割する)
5)作成日付
6)相続人全員の署名、実印押印
印鑑証明書も添付しておきます。
遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、レアケースではありますが、いくつか注意しなければならない点があります。ここでは遺産分割協議や遺産分割協議書作成上の注意点をお伝えします。
◇遺産分割協議は、必ず、相続人全員で行う。(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい)
◇「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
◇後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)はどのように分配するかを決めておく。(万一、記載もれがあっても、改めて協議書を作成する手間が省ける。)
◇不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
◇預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。
◇住所、氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
◇実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
◇協議書が数ページにわたる場合は割印をする。
◇協議書の部数は、相続人の人数分、及び、金融機関等への提出部数分(要確認)を作成する。
◇相続人が未成年者の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する。
◇法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う。(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)
◇相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
◇形見分けは自由にできる。(形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けることです)
◇相続人の1人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
◇相続人の一人が無断で遺産を処分してしまったら、他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てることができる。(第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば、返却する必要はありません。)
遺産分割協議が成立した後においては、相続人全員の合意がなければもう一度遺産分割協議をやり直すことは原則としてできません。ただし、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。
ただし、相続人全員の合意によって遺産分割協議をやり直した場合、税務上は遺産分割ではなく財産の譲渡・交換・贈与として課税される恐れがありますので注意が必要です。
やり直しが認められるケース
やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。
1)遺産分割時に相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合 (例 相続人が他の相続人に騙されていた)
2)分割後に、分割時の前提条件が変更された (例 あらたに遺産が発見された、新しい相続人が現れた)
遺産分割協議と遺産分割の種類とその方法にはそれぞれ数種類あります。ここではそれらを一つ一つ詳しくご説明します。
相続人が複数人いる場合、財産の分割協議が整うまで相続財産は共同相続人の共同所有となります。また同時に、その分割方法について協議をしなければなりません。遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。
【指定分割】
被相続人が遺言によって遺産分割の方法を指示する方法
【協議分割】
共同相続人全員の協議により行う分割方法
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視をした場合の分割協議は無効になります。遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。つまり、仮に遺言によって相続財産がゼロになったとしても、遺産分割協議で共同相続人の合意があれば、遺産分割は成立します。
遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。
遺産分割をする場合、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つの方法があります。上記の方法であれば、どのような方法で分割しても構いません。
【現物分割】
遺産を現物(建物や土地等)のまま分割する方法です。
例えば、Aは不動産、Bは現金を相続するというような場合です。分割の原則的方法ですが、相続人間の相続財産額に格差が生じる可能性があります。
【換価分割】
遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法です。
売却の困難な財産ではこの分割方法は使えません。
【代償分割】
特定の相続人が現物を取得する代償として、他の相続人に対して金銭を支払うという方法です。
また、被相続人の経営する会社の株式を後継者が取得する場合や遺産の分割が困難な自宅などである場合に用いられます。
相続人の間で協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の審判」を申し立てることができます。まずは「調停」を申し立て、それが不調なら「審判」による分割を行います。
【調停分割】
調停分割とは、家庭裁判所において家事審判官1名と調停委員2名以上が当事者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。
内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。合意が成立しない場合、調停は不成立となります。
【審判分割】
調停分割で合意に達しなかった場合に行われます。
審判分割は、家庭裁判所の判断によって分割方法を定めるように申し立てる方法です。相続には、「争族」という言葉があるように、遺産分割をめぐって親族間で争いとなってしまう危険性があります。
![]()
遺産分割協議でもめる原因は様々ありますが、その主な理由は、各相続人の事情や見解の差によるものがほとんどです。トラブルを避け、円満な相続を行う為にも、ここでは遺産分割協議でもめないためのポイントをご説明します。
遺産分割協議でもめる原因は、相続人・被相続人・その他親族の言動や状況による、各相続人の事情や見解の差によるものです。
・相続財産の大半が不動産で、各相続人への分割可能な財産がない
・相続財産全体がつかめない(財産目録が無い場合や不正確な場合)
・相続財産が各相続人の予想を超えて多い、または少ない
・被相続人が特定の相続人に多額の贈与をしていた
・相続人に、後妻、養子、非嫡出子などがいる
・相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする
・相続に関する知識を自分本位に解釈する人がいる
・遺産分割協議に参加しない人がいる
・相続人に自分の意見が無く、すべて人任せの人がいる
・相続人の中にまとめ役がいない、またはまとめ役が信頼されていない
協議をする前に財産目録や法定相続割合、遺留分などを整理しておき、話し合いの土俵を用意しておくことが大切です。
遺産相続争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。
・時間をいたずらに浪費する
・精神的にも体力的にも消耗する
・余計なお金が掛る
・遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる
相続争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。費用対効果では効率がよくありません。お互いのことを考え、話し合いの中でお互いにある程度譲歩できる落としどころを探すことが大切になります。
遺言がなくても相続は行えますが、その家族に合った相続を行う為には遺言は欠かせません。ここでは遺言を作成する意義、そして、上手な利用方法を説明します。
遺言は、法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、遺産に関する権利関係の帰属を、遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。
つまり遺言がない場合には、法定相続分に従って分与されますが、それぞれの家庭にはそれぞれの事情があり法定相続分によることが必ずしもベストな方法とは言えません。遺言によってその家庭の実情にあった遺産の分配を実現することができるのです。
むしろ、相続は遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないと言っても過言ではありません。
残された家族や大切な人がご自身の遺産のために争い、取り返しのつかない事になってしまわないように、事前に、効力を持つ遺言を残しておきましょう。遺言書を書くということは、財産を持つ者の義務といってもいいでしょう。以下に挙げる意思をお持ちの方は遺言書を作成することをお勧めします。
・相続争いを防ぎたい
・遺産の分割方法を決めておきたい
・相続人以外の人にも財産を譲りたい
・認知したい子がいる
・遺産を与えたくない人がいる
・妻に全財産を残したい
財産が当事者から他人に渡る行為には、相続の他に「贈与」があります。相続と贈与、どちらがお得なのでしょうか?ここでは贈与について詳しくご説明します。
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続税の課税対象となることを確認すること
以上の4点です。
次に、実際の生前贈与のやり方を見てみます。贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。つまり、1月1日から12月31日までの1年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。2000万円まで課税価格から控除できます。
しかしながら、相続税は5000万円+1000万円×法定相続人の数という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。
一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減などの優遇措置があるからです。相続税対策として生前贈与を活用するには、まず、被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。この制度がよく使われる場合としては、土地・建物の相続等、多額のお金が動く時です。この場合には、相続税などに詳しい専門家に、しっかり確認しておいてください。
成年後見制度は、本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合に、本人を法律的に保護し支えるための制度です。ここでは、成年後見制度についてさらに詳しく述べていきます。
前述の通り、成年後見制度は、本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合に、本人を法律的に保護し支えるための制度です。
すでに判断能力が低下している方が、自ら進んでこの制度を利用することは考えにくく、ご家族や周囲の方がこの制度およびその利用方法や手続き等を理解して、地域の社会福祉の関係者や専門家等に意見を聞き、相談しながら本人を支援していくことが大切です。
成年後見人は、本人の財産を管理するともに、広範な代理権及び取消権を持つことから、本人に代わって様々な契約を結ぶなどして、本人が生活に困らないよう十分に配慮しなければなりません。
申立てのきっかけになったことだけをすれば良いものではなく、成年後見人等は、本人のために活動する義務を広く負うことになります。この制度を利用することで、現状のどんな問題点が解決するのかや、将来においてはどうなるかの見通しを持つことが大切です。
財産管理が出来ていない、介護保険を利用していない、認知症が進行している、ひとり暮らしである、親族間に財産トラブルがある、悪徳商法の被害にあうなど、成年後見制度利用の背景には様々な事情があります。
これらのケースで成年後見人がついた場合には、預金通帳の再発行・財産の調査・介護保険の利用開始・生活の見守り・療養看護の計画化・悪徳商法の被害回復等が図られ、本人の財産管理と身上監護が始まります。
家族や親族(4親等以内)の方が申立人になります。申立人には、申立ての時に家庭裁判所にて面接調査(即日事情聴取)を行うという運用がされています。
・申立費用は申立人負担が原則です。
・申立書類は、申立人が自ら作成するか、司法書士等の専門家に依頼するかを検討する
・自ら作成する場合は事前に家庭裁判所へ出向き、相談し、その内容を確認します。
申立人は、申立てにあたって後見人等候補者を、その人の承諾を得て申立書に記載します。
・親族のどなたが後見人等候補者として承諾して頂けるか
・親族等の後見人等候補者の方が、制度全体の主旨を理解しているか
・後見人等候補者を専門職(第三者)後見人に依頼するか
・後見人等の報酬は、家庭裁判所が、その後の後見事務と資産・収入をもとに決めます
・後見人等候補者が見当たらない場合にどうするか
遺言の種類にはどのようなものがあり、どれが遺言として法的に認められるのでしょうか?ここでは遺言について詳しく説明していきます。
遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。しかし、本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのも一つの方法だと言えます。また、遺言は共同で作成はできません。必ず個人単位で作成してください。
遺言の種類には、通常次の3種類があります。
▶自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。また、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
▶公正証書遺言
本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。公正証書遺言は、本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝える事のできる通訳を介して遺言を作成することができます。また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場で公正証書遺言を作成する際の証人になることができません。
▶秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
▶上記以外の遺言
以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際において、証人3人以上が立ち会をし、そのうちの1人が遺言を本人に代わって筆記し、各証人が内容を確認の上署名・捺印して作成することも可能です。そして遺言の日から20日以内に証人または利害関係人から家庭裁判所に遺言の確認の請求をしなければなりません。
また、本人が通常の方式によって遺言することができるようになった場合に、そのときから6ヶ月間本人が生存するときは、遺言は無効になります。 この遺言は、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。この場合の証人も、公証役場での証人資格と同様です。
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、本人自身が遺言作成することが望ましいです。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
ここでは自筆証書遺言の作成方法を説明いたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。
ちなみに自分で書くのではなく、公証人に作成してもらう公正証書遺言の方法もあります。
(1)全文を自筆で書くこと。
(2)縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆、サインペンなど何を使用しても構いません。
(3)日付、氏名も自筆で記入すること。
※「平成21年4月吉日」などは遺言書を作成した日を特定できないため遺言が無効になります。
(4)捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5)加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
▶自筆証書遺言のメリット
・作成費用がかからない
・内容を秘密にできる
▶自筆証書遺言のデメリット
・自分で作成するので、作成形式の不備により無効になる可能性がある
・無くしたり改ざんされたりする恐れがある
公正証書遺言とは、公証人が、遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものです。ここでは交正証書遺言について詳しくご説明します。
公正証書遺言とは、公証人が、遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。
(2)証人を二人以上決めましょう。
※推定相続人、受遺者およびそれらの配偶者並びに直系血族・未成年者・公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
(3)公証人と日時を決めましょう。
全国の公証役場で依頼でき、出向けない場合出張を依頼できます。
(4)必要な書類を集めます。
①遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
②受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
③財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
④預金通帳のコピー
⑤証人の住民票などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
▶公正証書遺言のメリット
・公証役場で保管されるので紛失や改ざんの恐れがない
・公証人が作成するので、ほぼ確実に遺言が実行できる
▶公正証書遺言のデメリット
・作成費用がかかる
・遺言の内容を証人に知られてしまう
遺言は相続人に発見されなければ、せっかく作成しても何の意味も持ちません。ここでは、相続人にしっかりと発見してもらえるよう、正しい遺言の保管の仕方をご説明します。
遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。身の回りでそのような場所を探してみてください。そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。
▶公正証書遺言の場合
・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
・遺言書の存在が明らかになって、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
▶司法書士・弁護士に頼む場合
・遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士・弁護士に保管を頼むという方法があります。
・司法書士・弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
・従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。
▶第三者に頼む場合
・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
・しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんなどの恐れがあり、後に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係もない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。
▶遺言書の検認(遺言書が見つかったら)
相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?公正証書遺言は公証人役場に保管されているので問題ありませんが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。
家庭裁判所では相続人等の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、検認日現在における遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続きです。遺言内容の有効無効を判断する手続きではありません。公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に封印のある遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。遺言そのものが無効になることはありませんが、違反者には5万円以下の過料が課せられたり、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。
▶遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が二通以上見つかった場合で、その内容が矛盾するときは、一番新しく書かれた遺言書の内容が適用されます。日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていたというケースもまれにあります。遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。
▶遺言執行
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士や弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
▶遺言の実行手順
1)遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2)相続人の相続割合に従って遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4)遺贈の受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
5)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる。
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった弁護士・司法書士にその職務を依頼することが望ましいです。弁護士・司法書士へは自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、公正証書作成を依頼したりできます。
また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。あらかじめ弁護士・司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。
遺言信託とは、銀行や信託銀行が遺言者と契約し、当事者の代わりに様々なことを行なうことです。また、遺言信託にはもちろんメリットもあれば、デメリットも存在します。ここでは遺言信託を詳しく説明します。
遺言信託では、銀行や信託銀行が遺言者と契約して、次のようなことをしてくれます。
・遺言書の保管業務
・財産に関する遺言の執行業務
・相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務
▶遺言書の保管業務
遺言書の作成後は遺言書を預かり、遺言者の死亡後、その遺言書を相続人に渡す業務です。
▶財産に関する遺言の執行業務
遺言者の死亡後、預かっている遺言書の内容の通りに遺産を分ける業務です。
▶相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務
遺産を分けることだけでなく、相続税の申告、不動産の名義変更など複雑な手続きを代行する業務です。税理士や司法書士などが相続人に代わってこれらの手続きを行います。
▶遺言信託のメリット
・遺言書の偽造や紛失を防ぐために安全といわれる公正証書遺言により、遺言書を作成してくれる。
・遺言書に書かれている内容を忠実に実行してくれる。
・税理士や司法書士などの専門家を探す手間が省ける。
▶遺言信託のデメリット
・銀行や信託銀行に依頼した場合、すでに相続争いが起こっている場合や相続争いが起こる可能性が高い面倒な遺言は、引き受けてくれない事がある。
・銀行や信託銀行に依頼した場合、その手数料が高額になることがある。
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方を不利益から守る制度です。ここでは、成年後見制度について詳しくご説明します。
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう家庭裁判所に申し立てをして、その方が法律行為をする時に同意を与えたり、その方を代理して契約などの法律行為をしてくれる人を付けてもらう制度です。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。
よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要な範囲の法律行為は本人が自由にすることができます。
成年後見制度は本人の判断能力の程度などに応じて後見・保佐・補助の3つの制度に分かれています。
▶後見
精神上の障害により判断能力が欠けているのが通常の状態にある方が対象となり、審判があると、成年後見人が本人にかわって法律行為を行ったり、本人が単独でしてしまった法律行為を取り消したりできます。ただし日常生活に関する行為については取消しの対象になりません。
▶保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方が対象となり、審判があると、借金をしたり、保証人になったり不動産の売買をしたりなどの法律で定められた一定の行為について、保佐人の同意を得ることが必要となります。保佐人の同意を得ないでした行為については後で取り消すことができます。保護が必要な範囲を特定して保佐人に代理権を与えることもできます。
▶補助
軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な方が対象となり、審判があると、特定の法律行為について補助人の同意を得る必要があったり、特定の法律行為について補助人が本人にかわって法律行為をしたりできます。補助開始の審判を申立てるには本人の同意が必要となります。
成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。
・申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けて いないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
・申立書付票
・本人に関する報告書(用意できれば)
また、費用としては以下のものがかかってきます。
1)収入印紙
後見開始の申し立て
後見開始の申し立て 800円
保佐開始の申し立て
保佐開始の申し立て 800円
保佐開始の申し立て+同意権追加の付与の申し立て 1,600円
保佐開始の申し立て+代理権付与の申し立て 1,600円
保佐開始の申し立て+同意権追加付与の申し立て+代理権付与の申し立て 2,400円
補助開始の申し立て
補助開始の申し立て+同意権追加付与の申し立て 1,600円
補助開始の申し立て+代理権付与の申し立て 1,600円
補助開始の申し立て+同意権追加付与の申し立て+代理権付与の申し立て 2,400円
2)切手
各裁判所によって異なりますが、およそ3,000~5,000円程度です。
3)登記費用
成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。そのための費用として登記印紙4,000円分が必要となります。※収入印紙とは異なりますのでご注意ください。
4)鑑定費用
成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要があります。鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5~15万円程度です。
任意後見制度は、万が一の時の為に、後見事務の内容と「任意後見人」を、公正証書を作成し事前の契約によって決めておく制度です。任意後見制度には、様々なメリットもあればデメリットもあります。ここでは任意後見制度に関して詳しく見ていくことにします。
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と「任意後見人」を、公正証書を作成し事前の契約によって決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
分かりやすく言いますと、「今は元気でなんでも自分で決められるが、将来は認知症になってしまうかもしれない」という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が発症したと思った時に、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。任意後見制度は必ず公証役場で公正証書を作成する必要があります。
後見事務に必要な費用は任意後見人が管理する本人の財産から支出することになります。契約で報酬の定めをしたときは、任意後見人に支払う報酬も本人の財産から支出することになります。
任意後見契約を解除することもできます。任意後見監督人が選任される前であれば合意解除することも一方的に解除することもできますが、任意後見監督人が選任された後は正当な理由があるときに限って家庭裁判所の許可を得れば解除することができます。
公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
1) 公正証書作成の基本手数料 ⇒ 1万1,000円
2) 登記嘱託手数料 ⇒ 1,400円
3) 登記所に納付する印紙代 ⇒ 4,000円
この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは公証役場に聞いてみたほうが良いです。任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができることや、契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること、家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできることなどの良いところがあります。
しかし一方で問題点もあります。
・死後の処理を委任することが出来ない
・法定後見制度のような取消権がない
・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
・本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない
メリットデメリットをよく考えた上で、任意後見契約をするかしないかの判断をすることをお勧めします。
後見人はどのように選べばよいのでしょうか?後見人を選ぶにはいくつかのポイントがあります。ここではそのポイントを説明します。しっかりとした後見人選定ができるようになりましょう。
法定後見(保佐、補助を含む)の場合には、後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所が職権で選任することになっています。しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。
ただし、家庭裁判所の家事調査官が適格性を調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても別途選任されます。候補者が記載されていないときは、家庭裁判所が弁護士等から適任者を探して、職権で選任されます。
また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって異なります。過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いです。
しかし、最近は、身上監護は親族がなり、財産管理は弁護士とか司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあると言われています。財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いです。
また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
1) 未成年者
2) 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3) 破産者
4) 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
5) 行方の知れない者
6) 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
任意後見の場合に、誰を後見人に選ぶかについても、その人の状況によって異なります。身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんし、財産管理が中心であれば弁護士とか司法書士等の方が適切な管理ができるかも知れません。その場合、複数の後見人を選任する「共同後見」も検討に値します。
しかし、後見人にも将来何があるか分かりません。平均余命が長くなっている現状を考えると、将来的に最も安心なのは、信頼できる法人を後見人にする「法人後見」だと思われます。
現在、法人後見を実施しているのは、全国的には、司法書士会が設立した(社)成年後見センター・リーガルサポートがあります。また、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等が共同して「法人後見」を実施しております。
ここでは財産管理委任契約についてご説明します。財産管理委任契約にはメリット・デメリットがあります。そのことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
財産管理委任契約とは、自分で日常生活に必要な金銭の管理が困難な場合に、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、具体的な管理内容を決めて代理人に委任するというものです。その主な内容としては預貯金の管理や公共料金・医療費等の支払いなどがあげられます。
任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容や開始する時期も自由に定めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度が精神上の障害により判断能力の減退があった場合に利用できるものであるのに対し、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。ですから、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。
▶財産管理委任契約のメリット
・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
・財案管理の開始時期や内容を自由に決められる
・本人の判断能力が減退しても、財産管理委任契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能
▶財産管理委任契約のデメリット
・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
・成年後見制度のような取消権はない
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
見守り契約とは、自分の判断能力はまだ衰えてはいないが契約などの法律行為等について心配な場合に、定期的に訪問したり、電話で近況の確認をしたりすることを内容とする契約です。
訪問や電話によってご本人の判断能力等を確認し、任意後見契約の効力の発生タイミングを見極めるために契約されることがあります。
もし判断能力が低下していると判断した場合には速やかに家庭裁判所に対し任意後見監督人を選任してほしい旨の申立てをすることになります。
よって一般的には任意後見契約とセットで契約されることになります。また、遺言書作成時に契約するような場合もあります。
死後事務委任契約とは、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約です。死後事務委任契約を行うためには、様々な手続きやそれに伴う注意点があります。ここでは死後事務委任契約に関して、詳しくご説明します。
死後事務委任契約とは、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。委任者が、受任者に対し、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自分の死後の事務を委託する委任契約です。
委任契約は原則として委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができますので、委任者は受任者に対して死後の事務を委任することができます。
晩年の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために、財産管理委任契約、任意後見契約、見守り契約等の契約をするとともに、遺言をする方法が考えられます。
遺言で葬儀や法要のやり方を指定することは、それらが法定の遺言事項にあたらないため、葬儀や法要等に関する遺言は法律上の遺言事項ではなく、遺言者の希望の表明として遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。
最後の自己表現として葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、遺言者の生前に遺される方々に対して遺言者の希望をお伝えし、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことも大切です。
遺言では、遺言者の希望する葬儀が確実に行われるようにするために、祭祀の主宰者を指定することも必要になりますし、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。
▶契約内容の注意点
費用の負担について明確にしておく必要があります。任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了します。
見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
事前のご本人がご希望される内容にて、その費用分をある程度明確にし、その内容分の預託金として預けたとしても、相続財産に混在してしまう危険性や、預託が長期にわたる場合には、不正が発生する危険性があることを事前にご理解して頂く必要があります。
具体的な葬儀内容を生前に予約される方が増えていますが、葬儀会社にしても生前予約の反響は大きいです。また、80歳まで契約可能な保険を活用される方も増えています。生前予約された分の保障を保険とお考えのようです。
▶亡くなった後の事務手続き
・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務
それぞれを必要に応じて行うことも可能ですが、任意後見契約等は段階的な利用方法が考えられます。
「見守り契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」
の4点セットという考えで検討されることをお薦め致します。
任意後見制度は、ご本人が契約の締結に必要な判断能力がある時に、将来ご自分の判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ結んでおく契約です。「ご自分の後見の在り方をご自分の意思で決定する」自己決定意志の最大限度の尊重がその理念です。それと併用する契約や証書を知ることで、任意後見契約そのものが理解しやすくなります。
事業継承は会社の事業を後継者に引き継ぐ形で譲渡することです。会社の株式や事業用財産はもちろんのこと、役職やノウハウなどさまざまなものが含まれます。ここでは、事業継承について詳しくご説明します。
事業承継の方法には大きく分けて3つの選択肢があります。
1.親族が承継する 2.親族以外の従業員等が承継する 3.他社へ売却する(M&A)
事業承継には大きく4つのポイントがあります。
1.後継者の選定 トップの交代は、会社にとって非常に大きな問題です。特に中小企業の場合、社長個人の信用力で成り立っていることが多いのです。 それだけに後継者選びは慎重にならざるを得ません。
2.後継者の育成 会社は存続させていかなければなりません。後継者は経営学を学ぶ必要があるでしょう。
3.経営権の承継 会社法に則した経営権の承継です。ここを抑えないと経営権の争いの元になります。
4.財産の承継 税法に則した財産の承継です。事前準備が大切になります。
▶後継者の条件
今、会社を取り巻く環境は非常に厳しくなっています。 後継者に必要なのは、
・強いリーダーシップを持っていること
・人を活かすことができるひと
でしょう。
▶後継者が事前にしておくこと
・承継する会社の決算状況の把握
・会社の強みと弱みの把握
・金融機関との関係の把握(財務内容を知ること)
社長は後継者に「経営」について指導している人は多くありません。後継者は「経営」について誰から学ぶかわからなくて迷っています。社長は計画的に「経営」の基礎を後継者へ伝えていく必要があります。
・経営を学ぶ(活性化コンサルティング、財務体質強化コンサルティング、再建コンサルティング)
・現社長に学ぶ
・メンター(師匠)から学ぶ
・外部コンサルタントから学ぶ
・書籍から学ぶ
▶会社経営の承継
後継者はいますか?
YES ⇒ 事業承継者へ経営権の確保と集中
□経営者としての実務を習得
□株式・株式対策
□組織再編による対策 合併・分割・株式交換
No ⇒ 事業譲渡先の検討
□M&A・MBO・株式公開
財産の承継
後継者の選定が決まれば、財産の承継です。
財産評価に基づき、財産の移転をしていきます。
□財産評価の実施
□予想税額を把握する
□株式・不動産対策
□納税対策
□対策の実施
財産の把握と相続対策をしていますか?
YES ⇒ 株式対策とその他財産の対策
□株式対策
□土地・建物 その他の財産対策
□納税対策
No ⇒ 財産評価の実施
□財産評価の実施
将来的な事業承継を考えた場合、経営者はどのようなことをすれば良いのでしょう。ここでは事業継承のポイントをしっかりと見ていきます。
将来的な事業承継を考えた場合、経営者はどのようなことをすれば良いのでしょう。非上場株式や非上場企業の事業承継評価は、とても困難といわれます。
非上場会社の評価は相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類されます。その評価方法は純資産価額方式、類似業種比準方式、配当還元方式に大別されます。これらの評価方法は、会社の規模(資産総額・従業員数・売上高等)によって、以下のように変わります。
大会社……類似業種比準方式か純資産方式
中会社……類似業種比準方式と純資産方式の併用方式
(併用割合:類似0.6~0.9、純資産0.4~0.1)
小会社……純資産方式または類似業種比準方式と純資産方式の併用方式
(併用割合:0.5)
事業承継の対策として考えられるのは、事前に持株や不動産を贈与したり、他者に売却したり、長期的に効果のある対策をとることが重要になります。特に、小会社の場合には、経営者自身が所有する株式や、経営している会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続を考えて後継者へ集中させて引き継がせることが重要です。
利益が出ていたり資産があったりすると、株式の評価額が高額になり相続税の負担が大きくなってしまう可能性があります。このような場合、株式の評価を下げて後継者に譲渡したほうがよいでしょう。類似業種比準方式による場合は、配当・利益・純資産額を引き下げることが考えられます。純資産方式による場合は、内部留保を減少させるなどが考えられます。
不動産の場合ですと、経営者名義のものを会社名義あるいは後継者名義に
する必要がありますし、親族や後継者に売却する形式で同時に節税効果を狙ったりします。いずれにしても、どのような財産を引き継ぐかは、相続人となる親族も含めて、よく話し合い、お互いに納得することが必要です。
これを怠ると,会社経営を揺るがす事態になることもよくあります。
事業承継にかかわる問題は、税務や法務の専門知識を要することはもちろん、経営に与える影響も大きいので、経験豊富な専門家へ相談するなど、十分な検討が必要です。
種類株には様々なポイントがあり、注意点も存在します。種類株についてしっかりと学び、有効活用できるようになりましょう。
定款は分かりやすく言うと、会社と会社の所有者である株主との「契約書」です。従来の中小企業は、経営者(会社)=所有者(株主)であったため、「定款」が問題となることはありませんでした。しかし、事業承継(経営者の死亡)により株式が複数の相続人に分散する事で、必ずしも、経営者(会社)=所有者(株主)と限らなくなります。
また、株主の死亡により株主側に相続が発生した場合には、経営者(会社)が、全く知らない株主の出現という事態が発生する可能性も出てきます。このようなときに、「定款」をきちんと整備しておかないと事業承継者が、思わぬところで失敗をする可能性があります。
経営者(会社)=所有者(株主)のうちに、経営者にとって経営しやすい環境、つまり、定款の整備をしておく必要があります。相続人から株式会社の株式を買い取る規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自己株式の買い取り請求をさせない定款変更をするケースがあります。
種類株式には、その種類ごとに株主の権利に差をつけることができます。種類株式とは、簡単にいうと会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。
種類株式を上手に使えば後継者の経営権を確保することが可能になります。例えば、議決権制限種類株式を活用して、後継者には議決権のある株式を、それ以外の相続人には議決権のない株式をそれぞれ取得させて後継者に議決権を集中させる方法などが考えられます。
種類株式は、以下の9つ権利について異なった株式を発行することが可能です。もちろん、9つの権利のうちいくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能です。
1. 剰余金の配当
剰余金の配当に関する地位の優劣を定めた株式
2. 残余財産の分配
会社を清算したあと、残った財産の分配に関する地位の優劣を定めた株式
3. 議決権制限種類株式
株主総会での議決権の全部または一部を制限することを内容とする株式。この定めをした場合でも、その株主は種類株主総会では議決権を行使することができる。
4. 譲渡制限種類株式
その株式の譲渡に関して会社の承認が必要であることを内容とする株式。
5. 取得請求権付種類株式
株主が会社にその株式の取得を請求する権利が付与されている株式。
6. 取得条項付種類株式
会社が一定の事由が生じたことを条件としてその株式を取得することができる旨を定めた株式。
7. 全部取得条項付種類株式
会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる旨を定めた株式。
8. 拒否権付種類株式
株主総会において決議すべき事項のうち、その決議のほかに種類株主総会の決議があることを必要とする株式。
9. 種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる種類株式
その種類株主総会において取締役または監査役を選任する旨を定めた株式。
種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能種類株式総数も一緒に定款で定めておく必要があります。種類株式の発行の定款変更決議のときにあわせて定款変更をしてください。
平成20年2月に「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出されました。これによって、事業継承税制が新しく創設されました。ここでは事業継承税制について詳しくご説明いたします。
平成21年度税制改正で「取引相場のない株式などに係わる相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設されました。
税制改正の背景
1)これまでは、生前贈与で後継者に移転した自社株式についても、特別受益として遺留分の基礎財産に加えられるため、遺留分侵害分を取り戻されることがよくありました。
要するに、自社株式などを後継者へ移転した分は、遺留分権利者から遺留分の減殺請求をされた場合に、遺留分の算定の基礎財産に加えられ、遺留分侵害分が非後継者に移転する危険性があったのです。
2)相続税の算定にも問題がありました。現行の税法では、相続税の算定時に合算される額は贈与時の評価額ですが、民法上の遺留分の算定では「相続開始のときにおける価額」となっています。
そのため、生前贈与後に後継者の貢献により株式価値が上昇すると、上昇した分だけ相続時点の遺留分減殺請求の額が増え、後継者の事業承継意欲を阻害していました。
新税法で何が変わるのか
今回の「経営承継円滑化法」は、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例です。また、「株式等に係る納税猶予制度」は、事業承継の阻害要因だった相続税負担に対しての納税猶予措置なのです。
上記の2つの課題に対して以下の導入効果があると考えられます。
1)除外特例
この制度を活用することによって、一定の要件を満たす後継者へ先代経営者から贈与された自社株式、その他一定の財産について、後継者と非後継者との合意によって遺留分算定の基礎財産から除外できるようになります。
その結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になるのです。
2)固定特例
この制度を活用することによって、後継者と非後継者との合意によって、遺留分算定の基礎財産に算入される生前贈与株式の額を、当該合意時の評価額であらかじめ固定できるようになります。
その結果、生前贈与後の後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となり、後継者の経営意欲も阻害されなくなるのです。なお、合意する株式の価額は、その適正さを担保するために弁護士・公認会計士・税理士のいずれかの証明が必要になります。
上記2つの特例に関する合意をする場合に、非後継者が経営者から生前贈与等によって取得した財産についても遺留分算定の基礎財産に算入しないという合意をすることができるので、これによって後継者と非後継者の両者が納得できるように調整することが重要となります。
円滑な相続を行なうために、トラブルを防止する必要があります。ここでは相続に関するトラブル防止をする為のポイントをご説明します。
トラブルを予防するために効果的な方法の一つとして、生前贈与があります。生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、生きているうちにご自分の財産を実際に与えるということです。
贈与者本人は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能ですし、それを受けた人も、感謝の気持ちを直接伝えることができます。
相続税は、基礎控除・配偶者に対する税額減税措置・小規模宅地の特例などさまざまな軽減策が取られているのが特徴ですが、相続時精算課税制度を選択することも有効です。
これは贈与者が65歳以上の親で、受贈者が20歳以上の子である推定相続人の場合に、贈与財産の価額から特別控除として受贈者ごとに2,500万円が、相続時に清算される制度です。税法で贈与等には規定がありますので、事前に税理士に相談して下さい。
そもそも相続財産は、遺言者本人の財産です。生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後、財産を誰にどの位譲るかも、遺言者の自由です。ですから、遺言は遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って財産の分配を受ける事になります。相続人は遺言者の意思に反する財産争いをすることはできないはずです。
遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言には方式や様式に規定があります。法的な不備があると遺言をする意味がありませんので、財産の内容やそれをどのように分割できるかや、遺留分への配慮などについては、事前にご理解した上でないと逆効果になりかねません。
配偶者がいる方で全財産を配偶者に相続させたいときなどは、一旦一切の財産を配偶者に相続させるとの内容とともに、付言事項としてその配分をした理由や心情を記載した遺言を残されることをお薦めします。
いくら遺言書があるからといっても、遺言者がなぜそのような遺言をしたのかその真意がわからなければ、一部の相続人が納得せずトラブルに発展する可能性があります。付言には法的効力はありませんが、そうすることで、遺言によって相続分が法定相続分よりも少なくなってしまう相続人にも理解し易い内容となり、トラブル防止に役立つと思われます。
納付する相続税額を節税する対策には様々な方法がありますが、メリット・デメリットが存在します。ここでは、節税対策をご説明します。しっかりと学び、効果的な節税対策を行ないましょう。
相続対策でこれまでよく採用された方法に、無理な借金により、貸しマンションやアパートの建築をして財産評価額を下げるという方法があります。この方法には一定のリスクが伴うため、納付する相続税額を節税する対策は、あまりやり過ぎないようにすることをお薦めいたします。
そして、財産評価額を下げる対策より、現実的な問題として検討しなければならないのが、納税資金の確保です。現金や有価証券など換金しやすい資産を生前から準備しておき、相続発生後に直ちに換金することで相続税を納付しようとするものです。
特に、換金しにくい不動産等をあらかじめ換金化しやすいような資産構成に代えておき、納税資金を確保しておくことが重要です。不動産のまま残すのであれば、売却しやすい更地で持っておくこと、そして相続開始までの活用方法を検討することなどです。
注意点は、相続税課税時点において、納税義務者(特に配偶者)に、換金性の高い資金がきちんと引き継がれるような配慮を遺産分割との兼ね合いで「遺言書」等で記載しておくことです。資産を残す側としては、起こりうるであろうトラブルを想定して、最低限やっておかなければならないことがこの遺言書です。換金性の高い資産といっても、保有している土地取引には時間がかかるケースも多く、しかも譲渡所得税等の発生もあります。
物納する場合も物件自体が物納要件を満たしていることが求められ、更に認可手続に時間がかかります。しかも、物納認可が下りないといったケースもあり、これは大きなリスクです。そこで、相続税の納税のための資金準備をしておく必要性が発生するのです。
▶短期の対策としては…
納税資金対策として、よくご提案させていただいている方法をご紹介します。まず短期的なものとしては、
1)銀行から借入する
2)死亡退職金・弔慰金を活用
3)相続資産の売却
4)納税資金の生前贈与
5)延納・物納を利用する
があります。ただし、短期的というのは、狙ってそうするのではなく、そうしなければならなかった、ということが大半です。出来る限り計画的に、長期的な視野で取り組まれることをお薦めします。
▶長期の対策としては…
計画的に取り組めることの代表例が、以下の事項です。
1)生命保険に加入する
2)土地活用により賃貸収入を得る
3)賃貸用不動産を譲渡する
どれも税金と不動産のプロフェッショナルにアドバイスを求めた方が無難な対策です。信頼できるアドバイザーを探しましょう。
必要となる納税資金に対して、相続財産と相続人所有の金融資産(現預金・生命保険金・上場有価証券等)がいくら準備できるかを試算し、相続税を支払う能力があるかチェックしてみましょう。不足していれば、対策をうつことが必要となります。
一般に、相続税の支払能力の判定は、【納税資金÷相続税×100】で求めます。この比率が100%よりも小さければ小さいほど対策が必要です。
納税資金の不足を解消するためには、
(1)節税対策により相続税額を軽減すること
(2)納税資金対策により資金を増やすこと
の両面からのアプローチが必要です。
納税資金対策では「生命保険」の上手な活用が最も有用です。終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。支払保険料は相続税の分割前払いと考えることもできます。これにより、所有土地等を譲渡または物納することなく、相続税の納税を完結させることもできます。
相続財産が多額ではなく、生命保険加入が可能な年齢と健康状態であれば、生命保険の加入だけで相続税対策は十分なこともありえます。大きな節税効果は期待できませんが、少ない保険料負担で必要な相続税の納税資金を準備できれば「小さなコストとリスク」で「大きな効果」を上げることができます。すなわち、相続財産を無傷で残すために生命保険を活用し、死亡保険金で相続税をカバーすればよいのです。
相続税の納税資金を生命保険だけで準備することは理論的には可能ですが、被保険者が高齢の場合には保険料も相当な金額になる可能性がありますのでよく考える必要があります。
相続税の対策については大きく分けて2つの柱があります。1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。
2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。ここでは節税対策をより詳しくご説明いたします。
相続税の対策については大きく分けて2つの柱があります。1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。 2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。
▶生前贈与によって相続税を節税する
これは生前中にあらかじめ財産を相続人に贈与して、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。
具体的には、相続人に保険料を毎年贈与し、その資金で子供が契約者となって保険料を支払うことにより相続財産の事前移転をします。このメリットは、親が死亡したときに子が受け取る死亡保険金は相続税ではなく一時所得として課税される点です。そのためには「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。
・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
・贈与税申告書を保存する
・110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
・親(贈与者)名義の預金口座から子(受贈者)名義の預金口座へ贈与金額を振込む
・贈与者は生命保険料控除を活用しない
・その他、贈与の事実を認定できるもの
・子(受贈者)名義の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は子がする
以上のほかにも、場合によって注意することがありますので、活用については生命保険会社などの専門家にご相談下さい。なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれ相続税の課税対象となるため、贈与効果はありません。
▶生命保険を使って納税金を準備する
これは、納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、このタイプの対策です。
具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。
そのほかに、保険契約者および被保険者を相続人として、保険料負担者を被相続人とする生命保険契約をしている場合、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。生命保険契約に関する権利に対しては、相続開始まで支払っていた保険料に対して相続税が課税されることになりますが、その評価は支払済み保険料の70%から保険金額の2%を差し引いた額が評価額となります。
なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、それまでに支払っていた分に関してはかなりの節税効果が期待できます。相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、実行していただきたいと思います。
納税(資金)対策や節税対策には様々な方法がありますが、生命保険を活用した遺産分割対策が有効な手段の一つになります。ここでは生命保険を上手に活用する方法をご紹介します。
納税(資金)対策
相続税は金銭で一括納付が原則です。そこで生命保険が役に立つわけですが、なかでも「終身保険」が最適です。保障が一生涯続くので、死亡時には必ず保険金が受け取れるからです。
しかし、相続税額に見合う分の保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。その対策として、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用でき、以下のメリットがあります。
1)受け取る死亡保険金には非課税枠があります。
契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。
例えば、夫が死亡して妻が3,000万円の保険金を受け取った場合で、子供が3人いたとすると、法定相続人数4人×500万円=2,000万円が非課税となり、残りの1,000万円が他の相続財産と合算され、課税対象となるだけなのです
2)加入と同時に納税対策ができます。
加入と同時に何千万円という資金準備ができます。これが銀行預金などの積立との大きな違いです。
3)保険金受取時まで課税は発生しません。
銀行預金では利息に20%の源泉徴収がされますが、生命保険の場合、配当金も受け取った保険金と一緒に相続財産となり、契約途中での課税は発生しません。
4)現金で受け取れます。
相続税は、原則として発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。ですから不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達することになります。もちろん延納や物納という方法もありますが、利子もかかる上、手続も面倒です。
※なお、相続財産を無傷で残すためには、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、保障額(保険金額)を決める必要があります。
商売をしている方で相続財産が店舗兼自宅のみで現金資産がほとんどない様な場合、遺産分割すると商売ができなくなってしまうということがあります。遺言で後継者に相続させるとしていても、他の相続人から遺留分減殺請求をうけると、結局は店舗兼自宅を売却して遺産分割せざるをえなくなってしまいます。このような場合、生命保険を利用した「代償分割」という方法が使われます。
「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産をその代償として支払うというものです。この場合、代償分割の支払いのための資金を生命保険で準備することになります。ですから、店舗などを相続する後継者を死亡保険金受取人に指定しておけば、一度受け取った保険金を他の相続人に代償として支払うことができ、店舗などを売らなくてすみます。
※遺産分割対策は商店などを経営している場合だけでなく、会社経営者の場合も必要です。
同族会社などの場合、株式の多くを社長が持っているケースが多いようです。また、会社を子供に継がせたいと希望している経営者も多いようです。こういった場合、社長が死亡して保有していた株式を会社の経営に関係のない、後継者以外の非協力的な相続人に相続させると、承継後の経営が不安定になったり、会社に対して自社株の買い取り請求を受け経営を圧迫するといった事態にもなりかねません。
会社経営を安定的に承継するためには、後継者や協力的な相続人のみに自社株を相続させることが必要です。そこで、上記の生命保険を活用した遺産分割対策が有効な手段の一つになるのです。
贈与税について正しく知り、巧く活用すれば、大きな節税対策になります。ここでは贈与税に関して、詳しくお伝えします。
贈与税は、相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果が増大します。例えば、子供3人、準備期間20年とすると、限度額いっぱいまで贈与を毎年していくと、110万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転が無税で行うことができます。
税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、一時に多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。
「連年贈与」とは、例えば毎年110万円づつ20年にわたって贈与した場合に、最初から2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ、贈与の初年度に2,200万円全額に課税されてしまうものです。2,200万円を贈与した場合の贈与税は820万円となります。贈与税は税率が高いので連年贈与認定された場合は多額の税額が課されてしまいます。
連年贈与認定を避けるためには、
・贈与契約書を贈与の都度作成する。
・受贈者本人の預金口座への振込み・あえて110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す。
・毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。
といった対策があります。
年間110万円までは、無税で贈与することが可能ですが、相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。
そのような場合には、相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。
相続時精算課税は少々複雑です。それだけに、相続時精算課税について知っていれば、大きな節税に繋がります。ここでは相続時精算課税について詳しく見ていくことにします。
相続時精算課税とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります(相続時精算課税制度を選択しようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の届出書とともに贈与税の申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。いったん相続時精算課税制度が適用されると、当該贈与者が亡くなるまで制度の適用が継続されます。選択の撤回はできませんので注意が必要です。
なお、平成25年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除のほかに、700万円の住宅資金特別控除額を控除することができます(相続時精算課税制度における住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例)。
将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税されます。相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。支払った贈与税額が相続税額より大きいときは、差額が還付されることになります。
相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
財産を贈与した人(贈与者)
………65歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)
………20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。
相続時精算課税制度には一定の住宅を取得するための費用、または住宅の一定の増改築のための資金について、65歳未満の親からの贈与も適用の範囲とし、2500万円の非課税枠に加えて、1000万円を上乗せし、3500万円までを非課税の対象とする特例があります。
ただし、この特例を受けるためには、平成15年1月1日~平成21年12月31日までの贈与によって取得する資金であり、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋に同日までに居住するか又は同日後遅滞なく居住する必要があります。
| 相続時精算 課税制度 |
暦年課税 制度 |
|
| 贈与者 | 65歳以上 住宅取得資金の場合は年齢制限なし |
年齢制限なし |
| 受贈者 | 20歳以上の贈与者の推定相続人 (子、もしくは孫) |
年齢制限なし |
| 基礎控除 | 限度額2,500万円を複数年にわたって利用 | 年110万円 (毎年利用可) |
| 税率 | 一律20% | 10%~50% (6段階の累進課税) |
| 相続時の 取り扱い |
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。控除しきれない贈与税は還付されます。 | 相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。 |
住宅取得資金の特例というのは、贈与の際、家を建てるときの資金を両親などから援助してもらった場合は、贈与税が大幅に軽減されるというものです。
※以下の特例は「相続時精算課税制度」の新設により、経過措置を経て平成17年末で廃止されました。
※以下の特例は「相続時精算課税制度」の新設により、経過措置を経て平成17年末で廃止されました。
住宅取得資金の特例というのは、贈与の際、家を建てるときの資金を両親などから援助してもらった場合は、贈与税が大幅に軽減されるというものです。平成13年度の税制改正で、贈与税の基礎控除額(非課税となる金額)が60万円から110万円に増額されました。それにともなって贈与の特例の非課税枠も300万円(60万円×5年)から550万円(110万円×5年)に拡充されました。
これまでは、はじめて住宅を取得する人が対象でしたが、前述の改正で、「過去にこの特例を受けたことがない人が買い換えや建て替えを行うケース」や、「工事費が1,000万円以上または床面積が50平方メートル以上増加するような増改築工事を行うケース」でも、贈与の特例が受けられるようになりました。
たとえばこの特例を受けると、550万円までの贈与は無税になります。また贈与額が1,000万円の場合は税額が45万円ですみ、特例を受けない場合に比べて215万5,000円も節約できるわけです。(夫婦で特例を受けると1,100万円まで無税になります)
この贈与の特例を受けるには、下記で紹介しているように
「贈与を受ける人の条件」
「贈与をする人の条件」
「取得する住宅の条件」
を満たさなければなりません。
また贈与の特例も申告が必要で、確定甲告と同時に申告する必要があります。なお、贈与を受けた翌年の3月15日までに入居する、あるいは入居することが確実であることが条件となりますので注意しましょう。
▶贈与を受ける人の条件
・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円(給与所得の場合は約1442万円)以下
・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人またはその配偶者の所有する住宅に住んだことがないこと
・以前にこの特例を受けたことがないこと
・金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること
▶贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能
▶取得する住宅の条件
・床面積が50平方メートル以上であること
・店舗などの併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること
| 贈与額 | 通常の 贈与額 |
特例を 受けた場合 の贈与額 |
| 100万円 | 0円 | 0円 |
| 300万円 | 21万円 | 0円 |
| 550万円 | 84万5千円 | 0円 |
| 1000万円 | 260万5千円 | 45万円 |
| 1500万円 | 505万円 | 105万円 |
| 2000万円 | 714万5千円 | 260万円 |
夫婦間贈与というのは、婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,110万円まで贈与税がかからないという、配偶者控除が受けられる制度です。
▶制度の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
▶特例を受けるための適用要件
夫婦間贈与の特例を受けるためには、以下の条件に適合することが必要になります。
1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること。または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
▶適用を受けるための手続
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
1)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
2)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
3)居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
▶配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
1) 贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であることが条件です。なお、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
2) 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。従いまして、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることもできます。
この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。
(ア)夫または妻が居住用家屋を所有していること。
(イ)贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
▶不動産価格の算定
1)建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
2)土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。
死因贈与契約というのは、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との契約です。ここでは死因贈与契約について詳しく説明していきます。
死因贈与契約というのは、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との契約です。贈与の効力が贈与者の死亡によって発生する点で通常の贈与と異なり、民法上遺贈の規定に従うとされています。
受贈者は、当然ながら贈与者の考えを知り、それを踏まえて契約している事になります。ですから、贈与者の死後になって、放棄することはできません。ということは、贈与者の意思が確実に実現できるということです。
負担付とは、贈与者が生前の受贈者に一定の義務を課すことです。これと似たものに負担付遺贈があります。こちらは遺贈者の死後に一定の義務を課すものです。贈与者は死ぬ前に受贈者に義務(負担)を履行させ、負担と利益を受ける事ができます。
“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”
“同居して面倒を見て欲しい”
といったことが、負担として考えられます。
●負担付死因贈与契約の注意点
●負担付死因贈与契約に、公正証書を利用する
●負担付死因贈与契約の撤回
負担付死因贈与契約において、重要なのが、贈与の対象を正確に記載する事です。不動産の場合は、登記簿の記載に従って正確に記載しましょう。 また、預貯金は、 ・銀行名 ・口座の種類 ・口座番号 ・口座名義人 などを明示しましょう。 いずれにしても、死後になって、死因贈与の執行に疑問が生じたり、相続人との間で紛争が生じたりしないようにすることが、その目的です。 負担内容についても、具体的に明確にしておくことが大切です。死因贈与を円滑に、かつ確実に履行する為には、執行者を指定しておいた方が良いでしょう。というのも一般的に、死因贈与というのは、相続人と利害が対立するからです。 もし執行者の指定がない場合には、不動産の所有権移転登記の手続きに贈与者の相続人全員を登記義務者としなければならないため、手続きが困難になる可能性があります。執行に資格制限はありません。受贈者も執行者になれますが、弁護士や司法書士などの専門的知識を有するものを指定しておけば、より安心です。
負担のない単純死因贈与の場合は、遺贈の規定を準用していつでもそれを撤回することができます。しかし、負担付死因贈与の場合で、負担が全部または一部履行された場合は、遺贈の規定は準用されず原則として撤回することはできません。ただし、撤回することがやむをえないと認められる「特段の事情」があれば、遺贈の規定が準用され撤回することができます。
負担付死因贈与の場合で、負担が履行されなかった場合は、遺贈の取消の規定を準用して取り消すことができます。
負担付死因贈与契約の特徴を整理すると、
◇贈与を受ける人との契約が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇原則として取り消し・一方的な破棄は不可
となります。
遺言での遺贈とは違う法律行為ですが、効力の確定的な発生は贈与者の死亡のときです。被相続人がご自分の財産を処分するのですから、その意思が明確になっている事が必要です。それが書面にて作成されていて、負担の内容を明確にして贈与を受ける人との合意を必要としている負担付死因贈与契約は、遺贈よりも確実であるともいえます。
相続では、贈与された財産について遺留分減殺請求の行使を受けますので、過分な贈与については、紛争が予想されます。